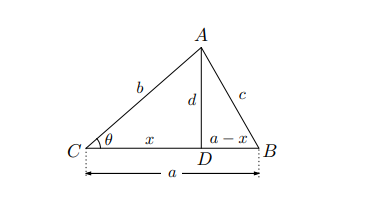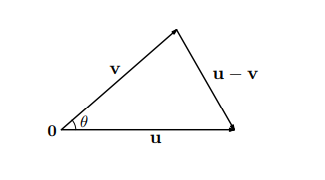ユークリッド空間上では, ユークリッド内積を考えることにより,「ベクトルの長さ」や「二つのベクトルの間の角度」といった概念を意味付けることができた。そのことを、復習を兼ねて反省してみよう。
先ず、ベクトル
が勝手にひとつ与えられたとして、ベクトル
の座標を用いてどのように表わされた、かということを考えてみると、
という式で与えられることが分かる。
全く同様にして、勝手な自然数
に対して、
という式で与えられることが分かる。
次に、
に対して、ベクトル
とベクトル
の間の角度について考えてみる。
いま、平面上の三角形
ABC に対して、点 A から辺 BC に下ろした垂線の足を点 D とする。
すると、
そこで、いま、
に対して、ベクトル
とベクトル
の間の角度を
として、
と
を二辺とする三角形に対して、いわゆる「三角形の余弦定理」(2)を適用することを考えてみると、
いま、二つのベクトル
が座標を用いて、
と表わせることが分かる。
以上の考察より、
上の標準的なユークリッド内積
は、座標を用いて、
というように表わせることが分かる。
すると、
上の標準的なユークリッド内積
は、次のような基本的な性質、
(イ) 双線型性: 勝手なベクトル と勝手な実数 に対して
(ロ) 対称性 : 勝手なベクトル に対して
(ハ) 正値性 : 勝手なベクトル に対して
という三つの性質を持つことが分かる。
例えば、(イ) の線型性は (4)式より
特に、(ハ)より、
上の標準的なユークリッド内積に関するベクトル
の長さは、
というように表わせることも分かる。
そこで、これらの
上の標準的なユークリッド「内積の概念」を、
上の線型空間
V 上の内積
に拡張して、(イ)(ロ)(ハ) を
に置き換えて、これらの条件を満たすときに、線型空間
V 上の内積と呼ぶ。
すると、内積を持つ線型空間 (
の長さは、
という式によって定めることができることが分かる。また、
として
これが、勝手な実数 に対して成り立つためには、右辺に現われる二次式の判別式 でなければならないから、
となることが分かる。この(5)式を Schwarz の不等式 と呼ぶ。
そこで、Schwarz の不等式を用いると、
となるような
実数 が存在することが分かるから, このような実数 として, 二つの元 のなす角度が定義できることが分かる。
すると、線型空間 V の元の「長さ」や二つの元のなす「角度」も, ユークリッド空間上のベクトルの「長さ」や二つのベクトルのなす「角度」としてイメージすることができる。
すなわち、、線型空間 V に正規直交基底を用いて線型空間 V を「番地割り」して考えることにすると、
というように同一視ができることになる。
さて、いま、二つのベクトル
が座標を用いて、
と表わされているとする。また、3 行 3 列の勝手な行列 A が
ひとつ与えられているとする。
このとき、内積
を考えてみよう。
(6)、(7)式より、勝手な実数
に対して成り立つ(イ)の双線型性、
行列では成り立たない(
)、ということが分かる。
このことをよくよく考えると、、内積
は、行列の積を用いて
というように表わすことができることに注意する。
そこで、
の間の内積
となることが分かる。
そこで、
とすれば、(10)式が成り立つことは分かるが、(10)式を満たす行列 だけだろうか。
いま、(10)式を満たす行列 が見つかったと仮定してみよう。すると、内積はスカラーであり、線型性をもつから、(10)式から(9)式を引き算してみると
でなければならないことが分かる。
以上から、与えられた行列
に対して、(10)式を満たすような行列
は、
しか存在しない、ということが分かる。すなわち、行列 A に対して, その転置行列
は、(10)式を満たすような行列として一意的に特徴付けられる。